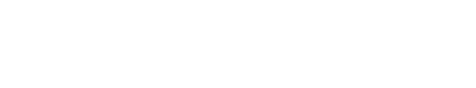2025/05/16
派遣先の雇用努力義務を解説。労働契約申込みみなし制度との違いは?
現代のビジネス環境において、人材派遣は企業の柔軟な人材戦略として広く利用されています。
しかし、派遣労働者の受け入れに際して、派遣先企業は法的な義務や責任を十分に理解し、適切に対応することが求められます。特に、「雇用努力義務」と「労働契約申込みみなし制度」は、派遣先企業が注意すべき重要なポイントです。
これらの制度の違いと具体的な対応策を理解することで、法令遵守と労働環境の向上を図ることができます。
1. 派遣先の雇用努力義務とは
1-1.雇用努力義務の概要
雇用努力義務とは、派遣労働者が一定期間以上同一の組織単位で就業した場合、派遣先企業がその労働者の直接雇用を検討し、努力する義務を指します。これは、派遣労働者の雇用の安定性を高めることを目的としています。
1-2.法的根拠
この義務は、労働者派遣法第30条の4に基づいています。
具体的には、同一の組織単位で3年を超えて派遣労働者を受け入れる場合、派遣先は以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
- 派遣労働者の新たな受け入れの中止
- 派遣労働者の直接雇用の申込み
- 派遣労働者の就業機会の確保を図るための措置
1-3. 適用条件
雇用努力義務が適用される条件は以下の通りです。
・同一の組織単位
派遣労働者が同じ課やチームなど、明確に区分された組織内で就業していること。
・3年を超える受け入れ
同一の組織単位での派遣労働者の受け入れ期間が3年を超える場合。
これらの条件が満たされた場合、派遣先企業は雇用努力義務を果たす必要があります。
1-4.雇用努力義務の具体的な措置
雇用努力義務を果たすために、派遣先企業が講じるべき具体的な措置には以下のものがあります。
・直接雇用の申込み
派遣労働者に対して、派遣先企業が直接雇用(正社員、契約社員など)を申し込むこと。
・派遣元への直接雇用依頼
派遣元企業に対して、派遣労働者の直接雇用を依頼すること。
・新たな派遣先の提供
派遣労働者に対して、他の適切な派遣先を提供すること。
・教育訓練の実施
派遣労働者のスキルアップを図るための教育訓練を実施し、雇用機会を拡大すること。
これらの措置を講じることで、派遣労働者の雇用の安定性を高めることが期待されます。
2. 労働契約申込みみなし制度とは
2-1. 制度の概要
労働契約申込みみなし制度とは、派遣先企業が労働者派遣法に違反して派遣労働者を受け入れた場合、派遣先がその労働者に対して直接雇用の申込みをしたものとみなす制度です。これは、派遣労働者の不安定な雇用状況を防ぎ、適正な労働環境を確保することを目的としています。
2-2.法的根拠
この制度は、労働者派遣法第40条の6に基づいています。具体的には、以下のような違反があった場合に適用されます。
- 派遣禁止業務への労働者派遣
- 期間制限を超える派遣労働者の受け入れ
- 偽装請負などの不適切な形態での労働者受け入れ
2-3. 適用条件
労働契約申込みみなし制度が適用される主な条件は以下の通りです。
・違法な派遣受け入れ
労働者派遣法に違反する形で派遣労働者を受け入れた場合。
・派遣労働者の意思
派遣労働者が直接雇用を希望すること。
これらの条件が満たされた場合、派遣先企業は派遣労働者に対して直接雇用の申込みをする必要があります。
また、派遣労働者の就業機会の確保を図るための措置(例:他部署での就業機会の提供、教育訓練など)を講じることも求められます。
これらの義務は「努力義務」と位置付けられており、法的に直接雇用を強制されるものではありませんが、厚生労働省や労働局からの行政指導が入る可能性があります。さらに、対応を怠ることで企業イメージや信頼性の低下にもつながりかねないため、非常に重要なポイントです。
2-3. 適用対象と例外
適用対象となるのは、いわゆる「一般派遣」や「登録型派遣」と呼ばれる形態で就業している労働者であり、専門26業務(例:ソフトウェア開発、通訳、翻訳など)については期間制限が撤廃されています。
一方で、以下の場合は雇用努力義務の対象外となるため注意が必要です:
派遣先が無期雇用の派遣社員のみを受け入れている場合
派遣労働者が別の組織単位へ異動となり、3年を超えていない場合
産休・育休・介護休業の代替要員としての派遣(一定期間に限られる)
3. 労働契約申込みみなし制度とは
3-1.制度の背景と概要
労働契約申込みみなし制度は、違法な派遣契約によって不当に労働力を利用される事態を防ぐため、2015年の労働者派遣法改正によって導入されました。この制度は、派遣先企業が法律に違反して派遣労働者を受け入れた場合、「派遣先がその労働者に労働契約の申込みをしたもの」とみなすことで、労働者保護を図る制度です。
この制度の大きな特徴は、「労働契約が自動的に成立するわけではない」ことです。みなしによって派遣先に申込みがあったとされても、労働者本人がそれを「承諾」しなければ、労働契約は成立しません。
3-2. 具体的な適用事例
労働契約申込みみなし制度が適用される具体的な例として、以下のようなケースがあります。
・派遣禁止業務への労働者派遣
建設業務、警備業務、一部の港湾業務など、法令で禁止されている業務に派遣された場合。
・派遣期間制限違反
派遣可能期間(原則3年)を超えて同一の派遣労働者を同一の部署で受け入れた場合。
・偽装請負
実態は労働者派遣であるにも関わらず、業務委託などの形式で労働者を受け入れていた場合(指揮命令関係が存在するなど)。
3-3. 企業に及ぶ影響
みなし制度により、派遣先企業は意図しない直接雇用の申込み義務を負うことになります。これにより、以下のような影響が生じる可能性があります。
- 勤務歴の引継ぎ(勤続年数のカウント)
- 社会保険加入義務の発生
- 賃金支払や賞与支給の対象者が増加
- 労使トラブルの可能性増大
派遣元が契約違反をしていても、派遣先の責任が問われるため、コンプライアンス体制の強化が不可欠です。
4. 雇用努力義務と労働契約申込みみなし制度の違い
4-1. 目的の違い
まず大きな違いとして、それぞれの制度が持つ「目的」が異なります。
雇用努力義務は、派遣労働者の雇用安定を促進するための制度です。一定期間、同一部署で働いた派遣社員に対し、企業が「直接雇用の道を用意するよう努力してください」というソフトな要請です。
労働契約申込みみなし制度は、違法な派遣就労に対する制裁的措置として設けられた制度です。「違法な受け入れをした以上は、労働契約を申し込んだとみなします」という強制力を伴う制度で、企業のコンプライアンス違反を是正する目的があります。
4-2. 法的強制力の違い
雇用努力義務
あくまで「努力義務」であるため、直接的な法的拘束力はありません。しかし、厚生労働省や労働局からの指導・是正勧告が行われる場合があります。
労働契約申込みみなし制度
法的拘束力があり、みなし申込みが有効になると、労働者が承諾すれば労働契約が成立します。派遣先企業は、望まぬ形での雇用義務を負うことになり、賃金や労働条件の整備が必要です。
4-4. 適用されるタイミングと条件
| 雇用努力義務 | 労働契約申込みみなし制度 | |
| 発生条件 | 同一部署で3年以上の派遣就労 | 違法な派遣契約が存在した場合 |
| 拘束力 | 努力義務(法的義務ではない) | 法的拘束力がある(申込みとみなす) |
| 労働者の同意 | 不要 | 必要(承諾により契約成立) |
| 主な目的 | 雇用の安定促進 | 違法派遣の是正 |
このように、両制度は対象も目的も大きく異なり、誤った理解により派遣先企業が思わぬリスクを抱えることもあります。
5. 派遣先企業が取るべき対応策
5-1. 契約内容・受け入れ期間の定期的な見直し
派遣労働者の受け入れが長期化する場合、定期的な契約内容の見直しを行い、以下の点を確認しましょう。
- 同一部署での勤務が3年を超えていないか
- 派遣元との契約内容が最新の法改正に準拠しているか
- 専門26業務の該当確認と記録管理
特に、受け入れ部署が複数ある場合、「部署異動により3年未満とする」形式が違法とされるケースもあるため、慎重な運用が必要です。
5-2. 派遣元との密接な連携
派遣元との契約関係は、単に書類上の関係にとどまりません。以下のような情報を日常的に共有する体制が重要です。
- 派遣社員の就業状況や勤務内容
- 労働者からの相談内容や勤務上の問題
- 契約満了に向けた進捗状況(更新予定や雇用継続希望)
トラブルが起きてからでは遅いため、リスク管理の一環として、事前の情報共有を徹底しましょう。
5-3. 法令・判例に基づいたコンプライアンス体制の構築
派遣法の違反は、企業名の公表など社会的制裁に繋がる可能性があります。以下のような施策を講じることで、違反を未然に防ぐことができます。
- 労務管理者向けの法令研修
- 内部監査・チェックリストの運用
- 外部の社労士や弁護士との連携体制
また、厚生労働省のガイドラインや最新の判例を参考に、社内の運用マニュアルをアップデートしておくことも重要です。
6. まとめ
派遣労働者の受け入れに際しては、派遣先企業にも法的責任と対応義務が発生します。雇用努力義務は、労働者の雇用安定を図る「努力」にとどまる制度ですが、労働契約申込みみなし制度は、違法行為に対する「制裁」としての意味合いを持ち、企業にとってのリスクは非常に大きくなります。
これらの違いを正しく理解し、派遣労働者の勤務状況・受け入れ体制・契約内容を正確に管理することで、コンプライアンスリスクを軽減しつつ、企業としての社会的信頼性も高めることが可能になります。
企業の人事・総務担当者様にとって、派遣労働に関する法制度の理解と対応策の整備は、単なる法令遵守にとどまらず、「採用戦略」や「人材定着施策」としての価値も持ちます。ぜひ本記事を参考に、貴社の運用体制を見直し、必要に応じて専門家と連携を図ることをおすすめします。 お電話でのご相談:0120‐085‐075
お電話でのご相談:0120‐085‐075
お仕事情報のおすすめ記事
-
2025/08/15
信頼を築く!明日から実践できるビジネスマナーの基本
-
2023/02/10
あなたの日常生活を支えるお仕事! 金属加工の仕事内容って?
-
2023/02/24
健康を支える大事な仕事 医療製造の仕事とは?
-
2023/04/28
女性活躍!!品質検査のお仕事とは?